TBS系列で放送されているドラマ「半沢直樹」の続編は回を追うごとに高視聴率を叩き出し、SNS上でも大変な盛り上がりようです。銀行を舞台とした経済ドラマでありながらこれほどの人気を博しているのは、良い意味での「時代劇っぽさ」も一因だと言われています。
現代を舞台としたドラマのはずなのに「半沢直樹」が時代劇っぽいと感じられるのはどうしてなのか、ドラマの演出面と前半の原作となった池井戸潤『ロスジェネの逆襲』から理由を考察してみました。「今どきこんな会社ありえない」と言われるほど権力闘争のドロドロ感を演出している点についても、元銀行員のベストセラー作家が書いた原作を知れば納得できるようになります。
「半沢直樹」が時代劇っぽいと言われる理由
言うまでもなく「半沢直樹」の舞台は現代であって、時代劇で人気が高い江戸時代や戦国時代ではありません。『ロスジェネの逆襲』を原作としたドラマ続編の前半はIT企業の買収がテーマとなっているせいか、パソコンやスマホなどいかにも現代的なツールが駆使されています。

表面的には現代の企業を舞台としたドラマでありながら「半沢直樹」が時代劇っぽいと言われるのは、それ以外の部分に何か理由があるはずです。その理由について考察する前に、まずは時代劇の定義を再確認しておく必要があります。
時代劇とは?
「時代劇」の定義には諸説ありますが、以下のような解釈が一般的となっています。
時代劇(じだいげき)は、日本の演劇や映画、テレビドラマなどで現代劇と大別されるジャンルとして、主に明治維新以前の時代の日本を舞台とした作品の総称である。(出典:時代劇 – Wikipedia)
時代劇の原作に使われてきた時代小説は、大正時代に新聞連載が開始された中里介山の大河小説『大菩薩峠』が先駆けとされています。この作品は江戸時代から明治時代へと移り変わろうとしていた幕末が舞台で、連載開始当初から見ればせいぜい50年ほど前の時代に過ぎません。明治時代の45年間で世の中が大きく変わったため、わずか50年前でも「時代物」として立派に通用できたのです。
この記事を書いた2020年の現在から見れば1970年が50年前に相当しますが、1970年頃を舞台とした小説では「時代小説」とは言えません。時代劇にしても同じことで、日本人の生活風俗が大きく変わった明治維新より前の時代を舞台としたドラマや映画が主な対象です。

そうした時代設定の定義以外にも、時代劇には現代のドラマや映画にない特徴が見られます。勧善懲悪的なストーリーが多いというのは江戸時代の読本や歌舞伎以来の伝統ですが、芝居がかった台詞や大げさな所作なども時代劇ならではの特徴です。戦国物に代表されるように、権力闘争に伴う人間ドラマが好んで取り上げられてきたのも時代劇の特徴に数えられます。
最近は江戸時代の庶民を描いた人情時代劇も人気を集めてはいますが、派手なチャンバラの立ち回りシーンは時代劇に欠かせないお約束として伝えられてきました。そうした特徴はドラマを面白くさせる要素として働いてくれるだけに、時代劇は庶民の娯楽として長く親しまれてきたのです。
「水戸黄門」やNHK大河ドラマとの共通点
時代劇に見られる以上のような特徴を兼ね備えてさえいれば、舞台がたとえ現代であっても面白いドラマが出来上がるのは当然だと言えます。ドラマ「半沢直樹」もまた善玉としての主人公や部下たちに対して、伊佐山や大和田常務(続編では平取締役に降格した姿で登場)・三笠副頭取など悪玉が対峙する典型的な勧善懲悪の構図です。
単純明快な勧善懲悪ストーリーという点では、長寿番組として人気を博した民放時代劇の「水戸黄門」にも通じる面があります。身分を隠して各藩に潜入した黄門様御一行が悪代官や商人らの悪事を暴き、お約束のチャンバラの立ち回りを演じた末、「この紋所が目に入らぬか!」と三つ葉葵を振りかざす爽快さが人気の要因でした。

半沢直樹は黄門様ほど絶大な権力を持つ存在ではありませんが、知恵と人望を武器に巨悪と戦う強さを持っています。最後は必ず半沢が勝つというお約束の展開が待っているだけに、視聴者も安心してドラマを楽しめるというわけです。伊佐山や大和田ら悪役を演じる歌舞伎役者の時代がかった演技も人気の一因で、現代のドラマに芝居の要素を盛り込んだ演出効果が逆に新鮮と受け取られました。
「半沢直樹」シリーズは銀行内部の権力闘争に伴うドロドロの人間模様を描いている点も特徴の1つですが、これはNHK大河ドラマに通じる要素です。大河ドラマで特に人気が高い戦国物では、織田信長や豊臣秀吉・明智光秀・武田信玄・上杉謙信ら戦国武将の権力闘争が中心テーマとなっています。現代ではありえないような権謀術数や駆け引きの数々も、生き馬の目を抜くような戦国時代ならありえただろうとして受け入れられてきました。
「半沢直樹」は現代を舞台としたドラマでありながら、同じような感覚で非現実的とも言える権力闘争が許容されてきた面があります。現役サラリーマンの大半が現実には味わいえない権力闘争を疑似体験できる場として、NHK大河ドラマ同様に「半沢直樹」が人気を集めているのです。
「今どきこんな会社ありえない」という声も
時代劇に付きものだった派手な立ち回りシーンこそありませんが、「半沢直樹」では激しい台詞の応酬がチャンバラの代わりを務めています。登場人物の顔を大写しにした「顔芸」は時として言葉以上の効果を発揮するだけに、高画質を強みとしたカメラワークも欠かせません。
一歩間違えれば過剰演出とも受け取られかねない極端な演技で時代劇さながらの権力闘争が繰り広げられているせいか、「半沢直樹」を見た人の中には「今どきこんな会社ありえない」という率直な感想を洩らす人もいます。就職できるのはほんの一握りでしかないメガバンクが舞台としても、ここまでドロドロの権力闘争は今の時代にふさわしくないと感じるのも無理はありません。

部下を激しく叱責する上司の姿は、現在の基準ではパワハラに該当する行為です。銀行内部の激しい出世争いや幹部クラスの主導権争いなども、これだけ露骨だとリアリティが感じられないという人も出てきます。そうした理由もあって「半沢直樹」は一種の時代劇という受け止め方をされているわけですが、ドラマの基本的なストーリーは原作に基づいているという点も忘れてはいけません。
続編の原作には登場しない大和田取締役がドラマ版では重要な役割を演じるなど、原作を改変している部分も確かにあります。それでもドラマで描かれる権力闘争の大枠は原作を忠実に再現したもので、視聴率を獲得するための過剰演出とは必ずしも言い切れません。「半沢直樹」を見て「今どきこんな会社はありえない」と感じたら、原作ではどのように書かれているか読んでみるのも一興です。
原作『ロスジェネの逆襲』が書かれた当時の状況
新型コロナウイルスの影響で予定より3カ月遅れて2020年7月にスタートした「半沢直樹」続編は、前半部分が『ロスジェネの逆襲』、後半部分は『銀翼のイカロス』が原作です。ともに人気作家の池井戸潤が過去に出版したベストセラー小説で、『オレたちバブル入行組』に始まる半沢直樹シリーズとしてはそれぞれ第3作と第4作に当たります。
破綻寸前の航空会社再建をテーマとした『銀翼のイカロス』に対し、『ロスジェネの逆襲』はIT企業の買収をめぐる経済ドラマがテーマです。作中で半沢直樹は東京中央銀行の子会社・東京セントラル証券に出向中の身となっているせいか、銀行と言うよりは証券会社を舞台とした経済小説の様相を呈しています。

『ロスジェネの逆襲』は2010年から2011年までの1年余りにわたり、「週刊ダイヤモンド」誌上に連載された長編小説に加筆修正されて2012年に出版された作品です。連載開始当初から10年以上が経っているため、必ずしも現在の経済情勢を反映していない部分はあります。
当時はまだ民主党政権下で経済的にはデフレが進行し、2011年に発生した東日本大震災の影響もあって日本経済は伸び悩んでいました。2012年12月に自民党が政権を奪還して安倍晋三氏が首相の座に返り咲き、翌年からアベノミクスの経済政策がスタートしたのは『ロスジェネの逆襲』が出版された後の話です。
タイトルの意味
当時の会社では「ロスジェネ世代」とも呼ばれる就職氷河期世代が若手から中堅のポジションを占め、バブル世代の上司との間でジェネレーションギャップが問題となっていました。『ロスジェネの逆襲』もそうした世代間の考え方の違いがテーマとなっており、銀行からの出向組と証券会社プロパー社員との対立と合わせて人間ドラマに深みを与えています。
ロスジェネ世代のプロパー組として鬱屈した感情を抱える営業企画部の森山も、当初は出向組でバブル世代の半沢部長に反発していました。仕事で協力し合ううちに理解を深め、森山は半沢を慕うようになるというストーリーです。
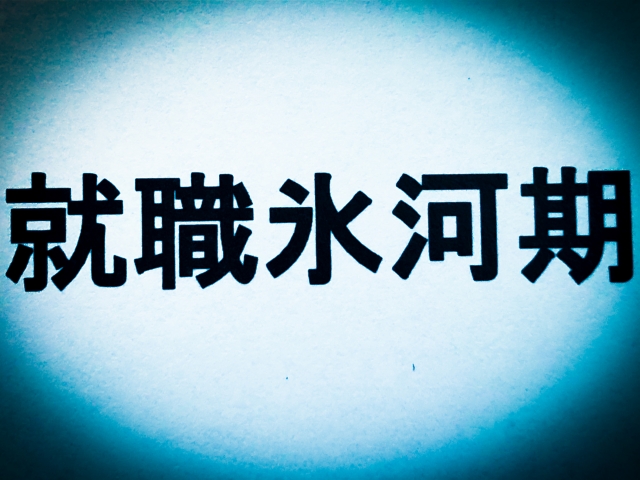
有能な部下として半沢直樹の「倍返し」を支えた森山は、敵対的買収の対象とされたIT企業・スパイラルの瀬名社長と中学時代の親友同士でした。その縁から半沢がスパイラル救済へと乗り出し、買収を主導する親会社の東京中央銀行証券部と対立する構図となります。
お硬いスーツ姿の男たちが登場人物の大半を占める中で、1人ラフな格好で登場する瀬名社長はライブドア社長当時の堀江貴文氏を彷彿とさせる人物です。そのライブドアによるニッポン放送の敵対的買収事件が勃発したのは、『ロスジェネの逆襲』の連載が始まった2010年の5年前に当たる2005年の出来事でした。作中で描かれたIT企業の買収合戦も、この事件に何らかの示唆を与えた可能性はあります。
半沢直樹の部下として働く森山もスパイラルを創業した社長の瀬名もロスジェネ世代の一員として、世の中への屈折した思いを持つ点では共通します。バブル世代の代表でありながら彼らに共感を示し、ロスジェネ世代にしかできないことがあると説く半沢直樹の言葉は、本作品でも最大の読みどころです。
原作者の経歴から読み解く時代背景
『ロスジェネの逆襲』そのものも今から10年前に連載が開始された作品だけに、時代背景がやや古くなっている点は否めません。わずか10年とは言え、2010年代で会社のあり方やIT技術は大きく変わりました。
ドラマ版では可能な限り2020年現在の状況を反映させるように工夫されていますが、カバーしきれない面も出てきます。「今どきこんな会社はありえない」という感想を持つ人がいるのも、原作の時代背景に伴うそうした違和感も一因です。
とは言えわずか10年の話でそこまで会社のあり方が根本的に変容してしまうとも考えにくいことから、違和感の背景にはまた違った事情があるものと見られます。銀行内部のドロドロした権力闘争はその最たる例ですが、これに関しては原作者・池井戸潤氏の経歴とも無関係ではありません。

1963年生まれの池井戸潤氏は半沢直樹と同様に、バブル景気真っ只中の1988年に当時の三菱銀行に入行した「バブル入行組」でした。優秀な学生が就職活動で大企業に厚遇されて囲い込まれた当時の経緯については、半沢直樹シリーズ第1作の『オレたちバブル入行組』冒頭にも書かれています。
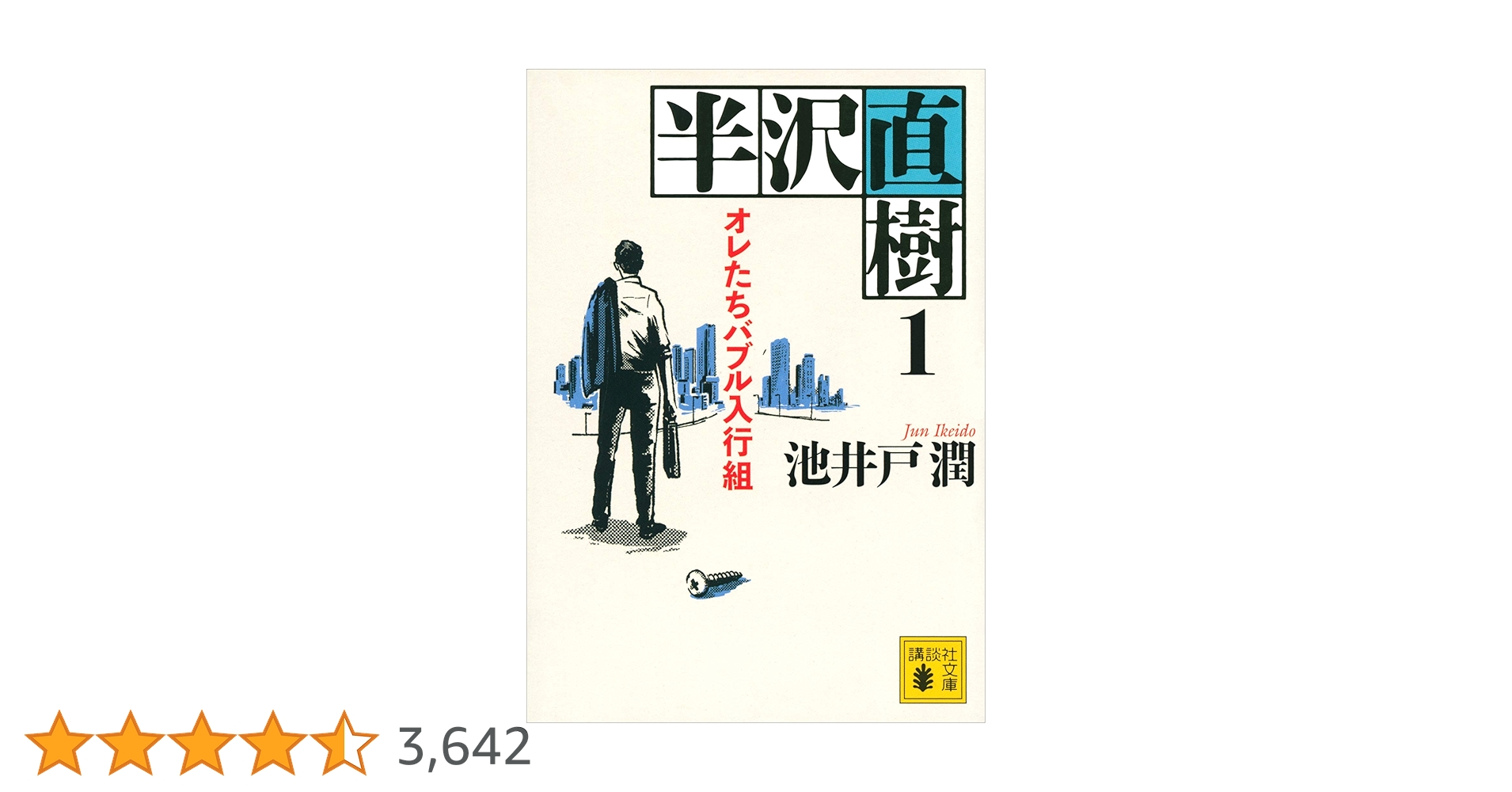
作者自身が半沢直樹のモデルというわけではありませんが、作者の実体験が何らかの形で作品にも反映されている可能性は大いにあります。執筆に当たっては何よりもリアリティが重視される中で、自分のよく知る業界の人物として半沢直樹という主人公を造形したのです。
作者が三菱銀行に在籍していたのはバブル崩壊後の1995年までで、1998年に江戸川乱歩賞を受賞して小説家としてデビューするまではコンサルタント業に従事していました。デビュー後も自らの経験を生かした銀行ミステリーを得意とし、『ロスジェネの逆襲』連載中だった2011年には町工場の奮闘を描いた『下町ロケット』で直木賞を受賞しています。受賞がきっかけとなって大ブレイクを果たし、ベストセラーの常連となったのは周知の通りです。
そんな作者の元銀行員という経歴を考えると、「半沢直樹」が時代劇と言われる理由も見えてきます。池井戸潤氏が銀行に在籍していたのはバブル期からバブル崩壊後に至る約8年間で、当時はまだ昭和の名残が支配的な時代でした。人口が多く学生の頃から激しい競争を強いられた団塊世代が企業の担い手だった当時なら、都市銀行内部でもドロドロの権力闘争が日常化していたとしても不思議ではありません。
『ロスジェネの逆襲』はIT企業が台頭した21世紀を舞台としながらも、銀行の体質としては作者が在籍していた当時の状況が何らかの形で反映されているものと推察されます。それからすでに30年も経った現在の常識から見れば、「半沢直樹」で繰り広げられる人間ドラマも「今どきこんな会社ありえない」と感じてしまうのです。
「半沢直樹」が時代劇と言われる理由まとめ

以上のような二重三重の理由で「半沢直樹」が一種の時代劇と受け止められているわけですが、それらの要素が相乗効果を発揮して面白さが倍増している点も見逃せません。昭和的なドロドロの権力闘争を描く際には、勧善懲悪ストーリーや芝居がかった台詞など時代劇に使われる演出が役に立ちます。
長らく「水戸黄門」を放送してきたTBSには、時代劇制作のノウハウが蓄積されていました。地上波での放送が終了して使う機会が減ってしまったノウハウを、現代ドラマの「半沢直樹」に適用して大ヒットを記録したのが2013年放送の前作です。7年というブランクを経て制作された続編は配役陣のアドリブ演技も加わり、時代劇的な演出に磨きがかかっています。
ドラマ版は原作をさらに誇張した内容とも言えますが、続編の前半で原作となった『ロスジェネの逆襲』も権力闘争の迫力という点では読み応えのある一冊です。ドラマの面白さを脳内で追体験してみたいという人は、ドラマ版よりリアリティが感じられる原作も読んでみるといいでしょう。




コメント
[…] […]