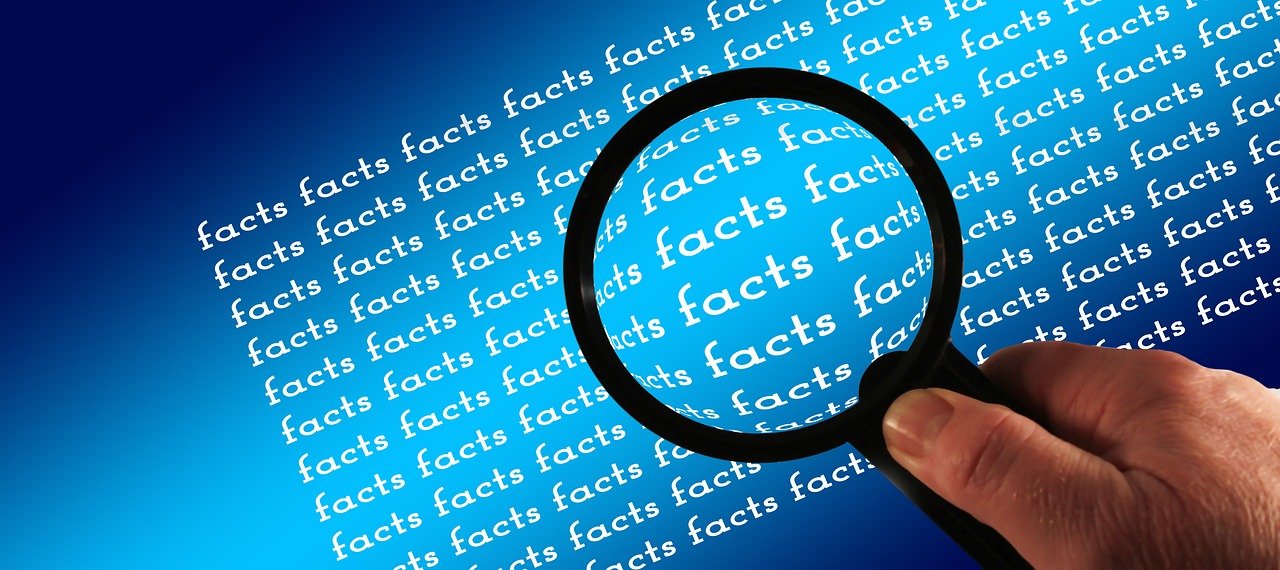エッセイと言えば作者の実体験について書いた文章と思いがちですが、「この人、話を結構盛っているな」と感じる場合も少なくありません。そのへんの解釈は人それぞれで、エッセイの書き方で混乱が生じている状況です。「エッセイに嘘を書いてはいけない」と主張する人もいれば、「話を面白くするためには多少の創作は許される」と言っている人もいます。
公募のコンクールで入選した作品も含め、エッセイに書かれている内容の100%が実話とは限りません。自分でエッセイを書く立場になってみると、「どこまで本当のことを書いたらいいのか」「フィクションの要素を盛り込んではいけないのか」といった疑問が出てきます。
筆者もエッセイの公募で入選歴はありますが、落選した例の方が多いのも事実です。一片のフィクション要素もない実話を書いて送ったのでは、なかなか受賞できないというジレンマも抱えています。そんな長年のもやもやを解消させるために、エッセイとノンフィクションとの違いについて考察してみました。
エッセイは100%実話…とは限らない
「エッセイはどこまでが実話なの?」という疑問に対しては、「100%実話のエッセイもあれば、そうでない作品もある」としか答えようがありません。エッセイの定義については人によってかなりの幅が見られる状況で、エッセイストの間でも1人1人違ったエッセイ観があります。エッセイ教室では「エッセイに嘘を書いてはいけません」と教えるのが一般的なだけに、受講した人の多くは100%実話のエッセイを書いているはずです。
書店には有名人の書いたエッセイ集も数多く売られていますが、それらのエッセイは全部が全部実話とは限りません。無名の一般人がブログ等で公開しているエッセイの中にも、実際にあった話を脚色している例は少なくないと見られます。
自治体や企業などで募集しているエッセイコンクールの受賞作は、まるで絵に描いたような感動話のオンパレードです。それらの全部が全部100%の実話なら、世の中には無数の感動に満ちていることになります。

実際には5~6dbぐらいの出来事を、文章のマジックで10dbに増幅したような話も少なくないはずです。こればかりは書いた本人にしかわかりませんが、実体験をありのままに書いたのでは面白いエッセイになりにくいのも事実です。無味乾燥になりがちな現実に味付けをして、面白い話に仕立て上げるのがエッセイの醍醐味とも言えます。
したがって面白い作品であればあるほど、「どこまで実話なの?」と疑ってかかる必要があります。中には事実をありのままに書いても十分に面白くなるほど数奇な経験をした人もいますが、ありふれた日常を味わい深いエッセイに仕立て上げるのは至難の業です。95%の実話に5%のフィクションを織り交ぜたぐらいが、エッセイを面白くする絶妙のさじ加減と言えます。
この場合の「フィクション」と言うのは、ありもしない話を捏造するという意味ではありません。むしろ演劇用語で言うところの、「脚色」や「演出」に近い概念です。SNSでインフルエンサーを演じながら、キラキラした日常を投稿している人の感覚に近いとも言えます。
そもそもエッセイとは?
以上のようなエッセイの現状についての解釈を目にして、「それは違う」と感じる人もいると思います。エッセイにフィクションの要素を盛り込むのは可能な否かという問題については、昔から意見が分かれていました。エッセイのコンクールで選考委員を務めるような先生方の中にも、エッセイのフィクション性を認める派と認めない派がいます。
本当のところはどうなのか、「エッセイ」が辞書でどのように定義されているのか調べてみました。
エッセー
- 随筆。自由な形式で書かれた、思索性を持つ散文
- 試論。小論。
出典:広辞苑(岩波書店)
エッセイ
- 自由な形式で自分の見聞・感想・意見などを述べた散文。随筆。随想
- ある特定の主題について論じた文。小論文。論説。
出典:明鏡国語辞典(大修館書店)
いずれも(2)の意味は西洋的な概念で、「序論・本論・結論」の形式で書かれる英文エッセイはこれに該当します。この記事で扱うエッセイは、随筆と同じ意味で使われている(1)の方です。
辞書によっても定義は微妙に違っていますが、「自由な形式」で書かれた「散文」という点では共通します。どちらも日本伝統の随筆を、エッセイと同じ意味に解釈されています。広辞苑で「随筆」を調べると、以下のように定義されていました。
随筆
見聞・経験・感想などを気の向くままに記した文章。漫筆。随想。エッセー。
出典:広辞苑(岩波書店)
つまりエッセイとは、見聞や経験・感想・意見などを自由な形式で書いた散文と定義されます。「経験や見聞に基づいて感想や意見を書いたもの」と定義してある辞書もありますが、少なくとも広辞苑や明鏡国語辞典では「基づいて」とは書かれていません。経験・見聞と感想(意見)は並列の扱いとなっていて、「など」を付けて含みを持たせています。
つまりエッセイには、「必ず経験した事柄を書かなければならない」と定義されているわけではありません。実際に昔ながらの随筆には、人から聞いた話や書物で読んだ知識を書いた例も多く見られます。
これが「見聞」に相当するわけですが、見聞は必ずしも実話とは限りません。作者にその話を教えた人が、実は嘘をついている可能性もあります。マルコ・ポーロの有名な『東方見聞録』も広い意味では随筆の一種ですが、伝聞に基づいた作品のせいか、「日本人は黄金の家に住んでいる」など事実とは信じがたい荒唐無稽な話も少なくありません。

見聞に基づいて書かれた話が実話でないとすると、エッセイ=随筆の作者も結果的に嘘を書いたことになります。作者自身の体験した事柄なら100%の実話になるはずですが、面白いエッセイにするために話を盛るような例があることも否定できません。文芸ジャンルとしてのノンフィクションと完全にイコールではないために、実体験を脚色した作品でもエッセイとして成り立ってしまうのです。
エッセイとノンフィクションとの違い
「エッセイとは何か」について解説した他のサイトの記事を見ると、エッセイもノンフィクションとして紹介している例が見受けられます。散文で書かれた文学作品を大雑把にフィクションとノンフィクションの2つに大きく分けるとすれば、エッセイも確かにノンフィクションの一種です。
狭い意味でのノンフィクションは数ある文学ジャンルの1つで、エッセイとは明確に区別されています。辞書が定義するノンフィクションの意味は、以下の通りです。
ノンフィクション
虚構をまじえず、事実に基づいて作りあげた散文作品。伝記・紀行・記録文学など。
出典:明鏡国語辞典(大修館書店)
ノンフィクション
文学のジャンルの一つ。虚構(フィクション)を全く排した散文。ルポルタージュ・旅行記・伝記・歴史など。
出典:マイペディア(平凡社)
つまり狭い意味でのノンフィクションとは、虚構を排した散文の文学作品という意味です。例に挙げられている伝記やルポルタージュなどのサブジャンルの中に、エッセイは含まれていません。他の辞書にも当たってみましたが、ノンフィクションの例としてエッセイを挙げている例は見つかりませんでした。
文学ジャンルとしてのノンフィクションは、ジャーナリズムと深く結びついている点が1つの特徴です。新聞記者が取材に基づいて記事を書くように、ノンフィクションライターが作品を執筆する際にも取材が欠かせません。

作者自身の体験を綴った自伝や手記もノンフィクションの一種に数えられますが、エッセイとは区別されてています。ノンフィクション作品は社会的なテーマを扱う例が多く、作者自身の感想より事実そのものの記録に重点が置かれています。
20世紀以降のノンフィクション作品には物語性を追求した例も多く、小説との境界が曖昧になっている状況です。事実に基づきながらフィクションの要素を加えた文学作品は、「ノンフィクション小説」とも呼ばれています。似たような現象がエッセイの分野にも及び、実体験を脚色したような作品も認められるように変わってきているわけです。
『おくのほそ道』にもフィクションあり
ノンフィクションを定義した辞書の解説には、「紀行」や「旅行記」もサブジャンルの1つとして挙げられています。俳人として知られる芭蕉の『おくのほそ道』は、江戸時代に書かれた紀行文学の古典です。紀行文学に分類されるからにはノンフィクションだと思いがちですが、実際にはフィクションの要素も少なくないことが後年の研究で判明しています。
自由な形式で書かれた散文の文学作品という点では、『おくのほそ道』も旅をテーマにした随筆=エッセイと見なすことも可能です。エッセイと言えば気楽な読み物というイメージもあるだけに、高度な文学表現を目指した『おくのほそ道』をエッセイと呼ぶのはおこがましい感もありますが。
『方丈記』や『徒然草』に代表されるように、古くからの随筆には文学的に優れた作品も少なくありません。エッセイが随筆と同じ意味だとすれば、『おくのほそ道』も旅をテーマにしたエッセイとして吟味してみる必要が出てきます。『おくのほそ道』に書かれている事柄の90%は事実だとしても、10%のフィクションが含まれている可能性があるからです。
旅に随行した弟子の河合曾良も、『曾良旅日記』という記録を残しています。研究者が両者を照らし合わせてみた結果、出来事の記述に食い違っている個所が数多く発見されました。『曾良旅日記』の方がノンフィクションとしての信憑性が高いと考えられることから、図らずも『おくのほそ道』の虚構性が浮き彫りにされたわけです。

©YAMATO2015
旅を続ける中ではいつもいつも理想通りに事が運ぶとは限らず、無粋な情景や不愉快な出来事に遭遇した日も少なくなかったはずです。芭蕉はそれらの夾雑物を捨象し、自らの理想とする旅の姿を『おくのほそ道』として昇華させたものと考えられます。その過程では事実にフィクションを加えた例もあったと思われますが、結果的には事実をありのままに書くよりも文学的完成度の高い作品が出来上がりました。
エッセイで「多少の脚色は許される」と考える人たちがいるのも、それと同じ理由によります。体験を題材としながらも、作品に仕立て上げる際には頭の中で事実を再構築する作業が欠かせません。作品の完成度を高くしようとすればするほど、再構築する過程で創作の要素が加わります。作中で描かれる会話などは、その典型的な例です。
実際に交わされた会話はもっと冗長で、文章にすると読みにくくなってしまいます。実際よりも洗練された会話に書き換えることで、エッセイの文章も引き締まります。ベースが実話であっても会話の部分を改変すれば、厳密な意味では創作と変わらない行為です。
同じようにして現実を再構築する作業は、会話以外の部分にも及びます。自分では実話を書いているつもりでも、頭の中で再構築した話は現実そのものではありません。「エッセイに嘘を書いてはいけません」と言っている先生方も、無意識のうちに事実を改変して作品を書いている可能性があります。
公募エッセイの応募作品に嘘を書くのはNG?
エッセイというジャンルは多少の創作を受け入れるだけの懐の深さもありますが、自治体や企業・団体で募集しているコンクールに応募する際には注意が必要です。そうした公募の多くはエッセイの募集と称して、実際には体験談の応募が想定されています。本来あるべきエッセイよりも対象が狭く、実質的にはノンフィクションの募集に近い状況です。
文章の書き方にはある程度の自由度が認められていて、狭義のノンフィクションほど記録性は重視されません。自由な書き方が認められているとは言っても、ありもしない出来事を捏造したり、事実の本質的な部分を改変したりするのはNGです。公募エッセイの主催者側は、あくまでも実話としてのエッセイを募集しています。

これが自身のブログで作品を公開したり、エッセイ集を電子書籍として出版したりする分には、エッセイをどのように書こうと自由です。虚実ないまぜのエッセイを発表したところで、責められる筋合いはありません。
エッセイのコンクールで受賞した人には賞金や賞品が授与される一方で、受賞作の著作権は主催者側に譲渡されるのが一般的です。受賞すれば賞金や賞品と引き換えに、自作のエッセイを主催者に売り渡す結果となります。応募者は主催者の依頼を受け、エッセイの執筆をコンペ方式で引き受けるのも同然です。
主催者に著作権を譲り渡した作品に対しては、自分の手を離れた後も作者としての責任が伴います。主催者側でエッセイに嘘を書くのはNGと考えているのであれば、応募者もそれに合わせるのが当然の務めです。「実話に限る」「実際の体験に限る」などと募集要項に記載されていないケースも少なくありませんが、エッセイの公募は基本的に体験談を書くものと心得ておく必要があります。
公募エッセイの受賞傾向
エッセイで収入を得る副業とは?公募やブログなど4つの稼ぎ方を解説でも言及したように、エッセイの公募ではすでに亡くなっている肉親や友人と絡めた作品が受賞しやすい傾向も見られます。その方が選考委員の共感を誘って高く評価されやすいのは事実ですが、こうした根本的な部分で嘘を書くのはNGです。
公募エッセイで何度も受賞してきた常連の中には、まだ生きている親や兄弟を亡くなったことにして感動のエッセイに仕立て上げている人もいました。こういう誤った「傾向と対策」が考え出されている点を見ると、公募エッセイの受賞傾向にも問題がありそうです。

エッセイはもっと多様な作品が評価されるべき文芸ジャンルですが、受賞傾向はあまりにも偏りすぎています。多少の創作を認めることでエッセイの表現は豊かになりますが、自由な書き方が可能な点を悪用する人も出てきます。
実際に募集されているのは本来の意味での自由なエッセイではなく、限りなくノンフィクションに近い体験談が大半です。事実の記述より感想の方に重点が置かれているために、「エッセイ」と称して募集されているものと考えられます。
この感想の部分が嘘か本当かという点については、書いた本人にしかわかりません。商業出版されているエッセイの中にも、話を面白くする目的でこっそり嘘を紛れ込ませている例は少なくないはずです。
当代随一のエッセイストとして人気の酒井順子さんも、エッセイのフィクション要素を肯定するような発言をしています。
「エッセイは書いた時点で全部うそ!_」酒井順子×長島有里枝 _ インタビュー
エッセイの公募は学校の作文の延長?
有名な文豪の太宰治も、嘘つき名人が高じて小説家にまでなった人物の1人です。処女作の『思ひ出』に「私が綴方へ真実を書き込むと必ずよくない結果が起ったのである」と書いています。
学校で作る私の綴方も、ことごとく出鱈目(でたらめ)であったと言ってよい。私は私自身を神妙ないい子にして綴るやう努力した。そうすれば、いつも皆にかっさいされるのである。
*筆者注:現代仮名遣いに改めています。「綴方」は現在の作文に相当する科目。
出典:太宰治『思ひ出』(青空文庫)
少年の太宰治が作文に「父母が私を愛して呉れない」という気持ちを正直に書いたところ、「受持訓導に教員室へ呼ばれて叱られた」という散々な結果を招いてしまいました。作文で自分の気持ちを偽って優等生を演じるようになってから、先生にも褒められるようになったというわけです。
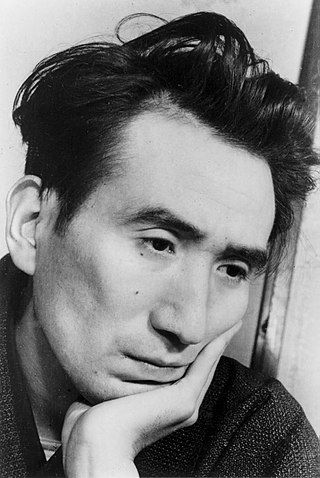
太宰治の体験は極端な例ですが、現代の小中学校や高校の作文コンクールにも不思議と符合する部分があります。大人を対象とした公募エッセイも、言ってみれば作文コンクールの延長のようなものです。そうでない公募もありますが、自治体が募集しているようなエッセイのコンクールの大半は優等生的な作品が好まれます。
作品の中で本当の自分でない優等生を演じるのは、心理的に抵抗のある行為です。少年時代の太宰治はそのへんを軽々と乗り越えたかのように見えますが、嘘をつくことの罪悪感に一生苦しむことになります。
筆者も同じように優等生を演じた作品でエッセイの公募に入選し、賞金を獲得したことが何度かありました。学校時代には作文や読書感想文で入選したことが一度もなかっただけに、「こうやって書けば受賞できる」というコツをつかんだように思ったものです。
しかしながら、感想の部分で嘘を書くのは度胸の要る行為です。嘘をつくことに耐えられないという人にはおすすめできない方法ですので、そういう人は事実そのままを書いても受賞できるような題材を見つけるしかありません。自分の気持ちを正直に書いても共感が得られるだけの自信がある人なら、100%実話のエッセイでも十分に勝負できるはずです。
まとめ
エッセイの定義が必ずしも明確ではないために、フィクションの要素を加えるのは可能か否かという点で混乱が生じています。否定派の人にとっては、エッセイは限りなく体験談に近いノンフィクションの一種です。感想の部分に重きを置いている点では記録文学や伝記(自伝)と異なりますが、本来あるべきエッセイのあり方を大きく制約してしまっています。
実際には出来事の順序や会話などを改変したり、感想の部分で嘘を書いたりているエッセイの例も少なくないはずです。現実の体験をエッセイに昇華する際には、頭の中で体験を再構築する必要があります。
その過程で多少の創作が加わる程度なら許されますが、まだ生きている人を亡くなったことにして感動話に仕立て上げるような書き方は感心できません。エッセイのコンクールでは完全にNGですので、「公募エッセイは実質的にノンフィクションの体験談を募集しているもの」と考えて応募作品を書く必要があります。